「夜勤がつらい。でも収入は下げられないから頑張るしかない」
私は高校卒業後、家庭の事情で進学をあきらめて無資格で介護士になりました。
職場には恵まれて、介護の楽しさや責任の重さ、学び続けることでご家族様・ご利用者様に喜んでもらえることが増え、働く喜びを知りました。
実務経験を積みながら介護福祉士の資格を取り、その後、高校卒業時に進学を希望していた保育士の専攻科に通信で通い、受験資格を取得するところまで進みました。
しかし、 介護と保育、あまりにも分野が離れていて、勉強のモチベーションが保てず受験資格を取得しても15年以上放置していました。
そんな私が、友人の誘いを機にサービス管理責任者に転職し、現在は児童発達支援管理責任者として働いています。
夜勤はもうしていませんが介護士時代よりも収入も上がりました。
子どもと過ごす時間も持ちながら、今はフルタイムで働き、独学で保育士試験に挑戦中です。
こんなふうに、夜勤が辛いけれど年収を落としたくない、身体も家族も大切にしながら働きたいと思い、少しずつ行動と選択を変えていった私の経験が、今、現場で働き続けることで悩んでいるあなたのヒントになれば嬉しいです!
夜勤を続ける生活に限界を感じていた私
夜勤を最低でも週1回はしないと、一人暮らしでは生活がままならない状況。
(両親が早くに他界していたため、私は実家に帰ることもできませんでした)
夜勤帯は人手も少なく、責任も重い。しかも体力的にもハードで、私は本当に夜勤が憂うつでした。
「夜勤は慣れだよ」
そう先輩たちには言われてきましたが、18歳から介護士として働き始めて、30歳になるまで一度も“慣れた”と感じたことはありません一回り以上年上の先輩が元気に夜勤をこなしている姿は、私にはまぶしくて仕方がなかったです。
夜勤明けの私は毎回「10歳老けたよ」なんて冗談を言われるほど、疲れ切っていました。
30歳で、介護士からサービス管理責任者への転職
体力的な厳しさを感じながらも、介護士の仕事は日々学びが多く、同僚や職場にも恵まれていたこともあり
私は「辞めたい」と思ったことはほとんどありませんでした。
そんな私に、ある日友人から声がかかりました。
「障がい者の就労支援事業所を立ち上げたいんだけど、サービス管理責任者をやってくれない?」
障がい福祉の分野はまったくの未経験。正直、不安は大きかったです。
でも——
“担い手が減っている農業を、障がいのある人たちの仕事にしたい”
というその理念に心を動かされました。
迷った末、私は30歳で福祉の分野をシフトチェンジすることを決意しました。
やり慣れた介護の世界を離れることは怖かったけれど、
「ここからまた何かを築けるかもしれない」と思えたのです。
生活支援と就労支援のギャップに戸惑った日々
就労支援の現場で働く前に、私は何度か勉強会に参加し「ある程度は理解しているつもり」でした。
でも、実際に現場に立つとやっぱり難しい。当たり前ですが、“やってみる”と見えてくることが全然違いました。
就労継続支援B型は福祉サービスでありながら、同時に「就労の訓練」でもあります。
つまり、ご利用者様に“仕事として作業してもらう”ことが前提になります。
作業に取り組んでもらえなければ、工賃もお支払いできないし、訓練としての機能も果たせません。
でも、実際には障がい特性によって、お話が止まらなかったり、途中で眠ってしまったりする方もいます。
生活支援であれば「できる範囲で無理なく」で済んだことも、
就労支援になると“業務として取り組んでもらう”ための工夫が必要になります。
「どうすれば無理なく作業に取り組んでもらえるか?」
面談を通じて背景や困りごとを探り、作業環境を見直す。そうした一つひとつの工夫が求められました。
“福祉”と“仕事”の間にある独特のバランス感覚。
私はこのギャップに、最初かなり戸惑い「これは、生活支援とはまったく違う世界だ」と実感しました。
サービス管理責任者はやりがい抜群。でも、忙しすぎた。
就労継続支援B型事業所の管理者として働くなかで、私はこう考えていました。
作業の種類が豊富なら、選択肢が広がる。通所してくれる人も増えるし、就職のイメージも持ちやすくなるはず!
その想いから、自主製品の開発や農福連携、内職作業の獲得に向けた営業など、とにかくがむしゃらに動きました。
県が主催する工賃向上研修にも参加し、就労支援の“経済的側面”を強く意識するようになったのもこの頃です。
「就労支援は支援だけじゃない。 利用者さんの収入にもつながる“仕組みづくり”が必要なんだ」
そんな気づきが、私の中に根付いていきました。
ありがたいことに、通所する利用者さんも少しずつ増えました。
スタッフの採用や育成にも関わるようになり、「良い職場環境をつくる楽しさ」も実感していました。
規模は大きくなかったけれど、スタッフや利用者さんの離職がほとんどなかったことが、私にとっての誇りでした。
けれどそんな中、結婚と妊娠を経て、私は自分の働き方を見直すことになります。
残業が当たり前の毎日にライフステージの変化が重なり「このままでは続けられないかもしれない」と感じたのです。
子どもの発達が気になって、不安で検索ばかりしていた日々
出産を機に就労支援B型事業所を退職し、
私は子どもが2歳半になる頃まで家庭で育児に専念していました。
でも、育児は「かわいい」だけでは済まされない**毎日でした。
子どもの成長や発達について、少しでも違和感と感じると、SNSやネットの情報をひたすら検索して、不安になる自分がいました。
健診で特に何も言われなくても、
小さなことが気になって眠れないような夜もありました。
そしてそれは、きっと私だけじゃない。
多くの親御さんが同じように、不安を抱えているのだと実感しました。
だからこそ、「また仕事に復帰するなら」私は子どもに関わる仕事を選びたいと思うようになったのです。
親としての気持ちを理解しながら、同じように悩むお母さん・お父さんたちに、少しでも安心してもらえる存在になりたい。そんな思いが、今の私の原点です。
児童発達支援管理責任者として社会復帰。保育士試験にも挑戦中!
私は介護福祉士としての実務経験を経て、障がい者就労支援のサービス管理責任者になり、
さらにその実務経験から、児童発達支援管理責任者(児発管)として就職することができました。
(私が児発管研修を受けた時と比べて、現在は要件が変更になっています。詳しくは別記事でまとめる予定です)
児発管として働き始めてからは、発達マイルストーンや応用行動分析(ABA)など、先輩職員から学びつつ、現場での支援に取り組みました。
でも、ふと感じたのです。
「国家資格を持たないまま、大切なお子さんの支援に関わっていていいのだろうか?」
「私は一生、子どもに関わる仕事をしていきたい」
介護の仕事をしながら通信制で2年間学び、受験資格をとったまま、仕事と試験勉強の両立が難しく15年以上、放置していた保育士試験に独学で挑戦することを決めました!
親も実家もなく、逃げ場も学歴も資格もなかった18歳の私。
たくさん失敗して、泣いて、遠回りばかりしてきたけれど、
少しずつ「軸をずらしながら」経験を積み重ねて、
子どものころに夢見た仕事に、41歳でようやくたどり着くことができました。
この道のりは、決してスマートではなかったかもしれません。
でもだからこそ、私は伝えたいです。
今の働き方にモヤモヤしている方へ
もう夢は無理だと諦めかけている方へ
自分に向いていないと思いながら、仕方なく働いている方へ
「こういうキャリアの描き方もあるんだ」
「私も、もう一歩進んでみようかな」
そんなふうに、未来を少しでも明るく感じられる発信ができたら嬉しいです。
転職にはリスクもあるけれど、転職活動はノーリスクです。
まずは、今の職種の給与相場を調べてみるのもおすすめです。
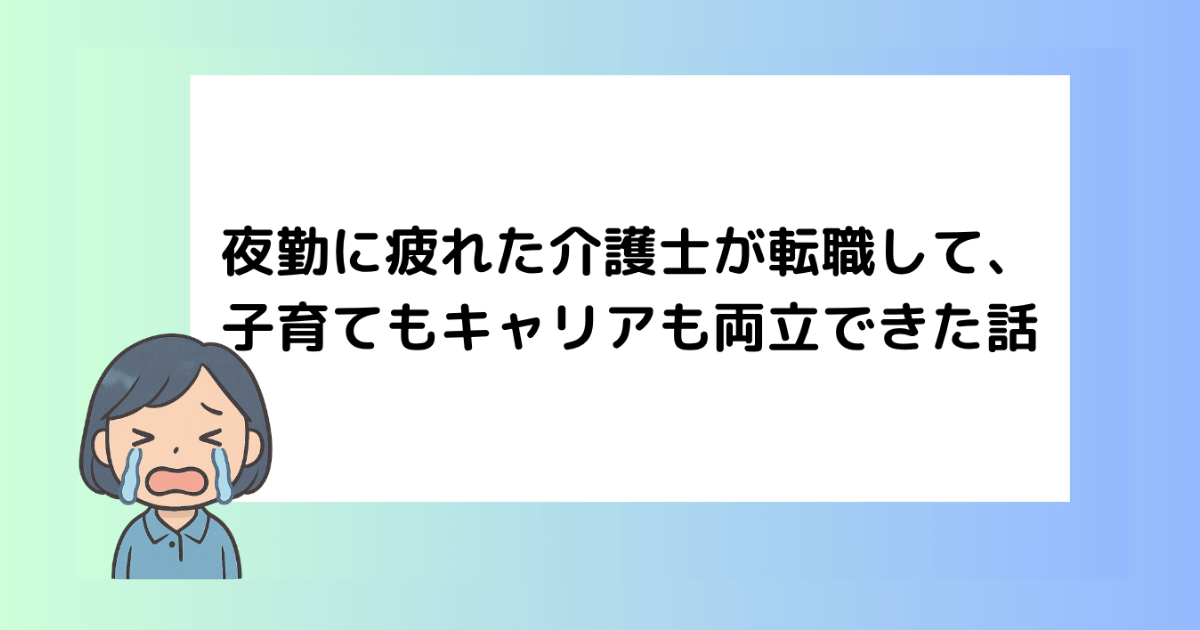
コメント